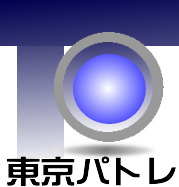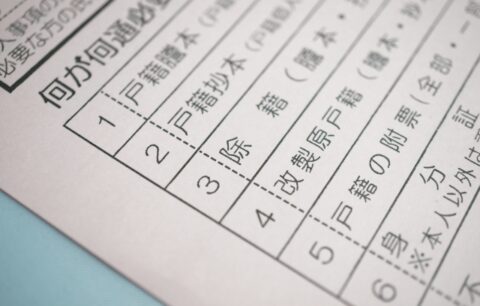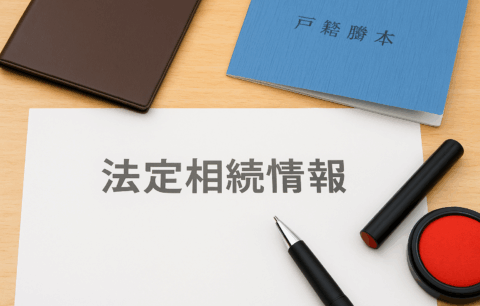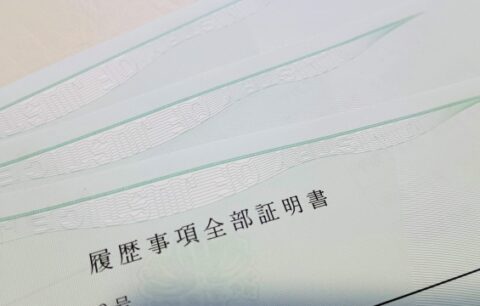遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、当事務所では確実に遺言が実行される「公正証書遺言」と推奨させて頂いております。
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは?公証役場で、公証人が遺言者の意思を聴き取り、作成する遺言書です。
証人2人以上の立ち会いが必要です。
専門家が作成するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。
証人2人以上の立ち会いが必要です。
専門家が作成するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは?この遺言書は、遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印することで作成できます。
最も手軽な方法ですが、形式に不備があると無効になってしまうリスクがあります。
さらに、死去後に自筆証書遺言が見つかった場合、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があります。
2020年からは、財産目録をパソコンなどで作成できるようになりました。
最も手軽な方法ですが、形式に不備があると無効になってしまうリスクがあります。
さらに、死去後に自筆証書遺言が見つかった場合、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があります。
2020年からは、財産目録をパソコンなどで作成できるようになりました。
遺言書作成の流れ
事前相談遺言書を作成する目的を確認
(例:相続人間の争い防止、事業承継、相続税対策)
財産状況や家族関係を把握
公正証書遺言か自筆証書遺言かを選択する方向性を検討
(例:相続人間の争い防止、事業承継、相続税対策)
財産状況や家族関係を把握
公正証書遺言か自筆証書遺言かを選択する方向性を検討
相続関係と財産の調査戸籍謄本で法定相続人を確認
不動産:登記事項証明書・固定資産評価証明書
預貯金:通帳、残高証明書
株式・保険など:証券会社・保険会社の資料
不動産:登記事項証明書・固定資産評価証明書
預貯金:通帳、残高証明書
株式・保険など:証券会社・保険会社の資料
遺言内容の設計誰に、どの財産を承継させるかを決定
代償分割や特定財産承継の希望を反映
遺言案の相続税の事前シミュレーションを作成
遺留分への配慮が必要かを検討
付言事項(家族へのメッセージ)も整理
代償分割や特定財産承継の希望を反映
遺言案の相続税の事前シミュレーションを作成
遺留分への配慮が必要かを検討
付言事項(家族へのメッセージ)も整理
原案の作成専門家(税理士・行政書士・弁護士)が文案を作成
相続人に誤解を与えないよう法律用語で明確に記載
税務上の影響(小規模宅地の適用可否、二次相続対策)も再確認してチェック
相続人に誤解を与えないよう法律用語で明確に記載
税務上の影響(小規模宅地の適用可否、二次相続対策)も再確認してチェック
遺言方式の選択公正証書遺言(当事務所の推奨):公証役場で作成。法的に最も安全で、銀行や法務局の手続きで確実に効力を発揮。
自筆証書遺言:法務局の遺言書保管制度を利用すれば紛失・改ざん防止が可能。
自筆証書遺言:法務局の遺言書保管制度を利用すれば紛失・改ざん防止が可能。
公証役場での手続き(公正証書遺言の場合)公証人との打合せ・文案調整
相続人以外の証人2名を手配(当職が証人になることも可能)
公証役場で読み合わせ、署名・押印
相続人以外の証人2名を手配(当職が証人になることも可能)
公証役場で読み合わせ、署名・押印
完成・保管公正証書遺言の場合:原本は遺言執行者又は依頼者が保管、副本を依頼者に交付
アフターフォロー財産や家族関係の変化に応じて 定期的に内容を見直し
見直しの都度、相続税の試算や二次相続対策を行う必要あり
見直しの都度、相続税の試算や二次相続対策を行う必要あり