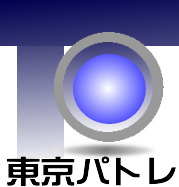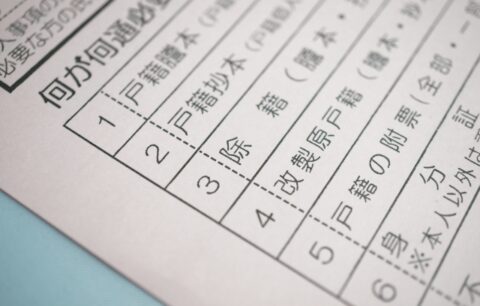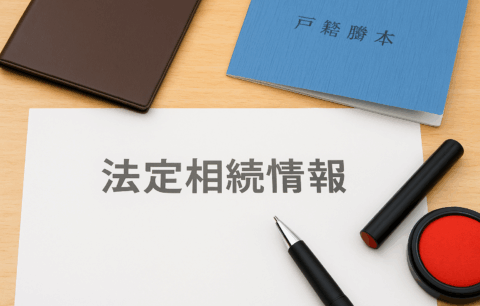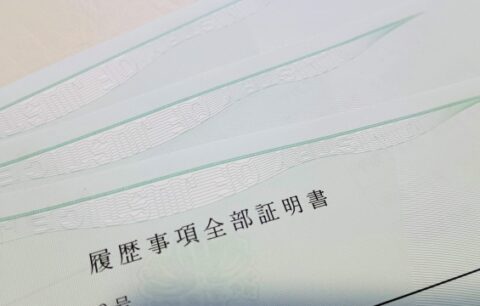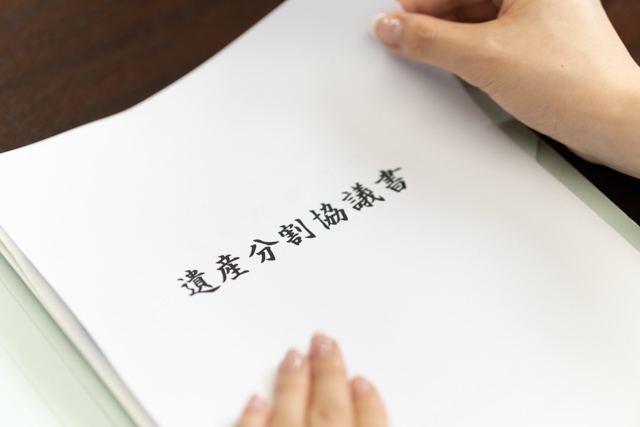遺産分割協議書作成の流れ
相続人の確定被相続人の出生から死亡までの 戸籍謄本を全て取得し、法定相続人を確定。
相続人に漏れがあると協議自体は無効になるため最初に必ず確認。
相続人に漏れがあると協議自体は無効になるため最初に必ず確認。
相続財産の調査・財産目録作成不動産:登記事項証明書、固定資産税評価証明書
預貯金:残高証明書、通帳
株式・投資信託:残高証明書
その他:保険金、車、貴金属など
負債も含めて一覧化(財産目録作成)
預貯金:残高証明書、通帳
株式・投資信託:残高証明書
その他:保険金、車、貴金属など
負債も含めて一覧化(財産目録作成)
遺産分割協議(話し合い)相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う。(事前に遺産分割協議書の案と相続税シミュレーションを作成しておくと良い)
<分割方法の例>
「現物分割(不動産は長男、預金は次男など)」
「代償分割(不動産を取得する代わりに他相続人へ金銭を支払う)」
「換価分割(財産を売却して代金を分ける)」
「共有分割(不動産を共有名義にする)」
協議書の作成協議内容を書面化する(書面がないと不動産登記や銀行手続ができない)
<協議書の記載項目>
「被相続人の氏名・死亡日・本籍」
「相続人全員の氏名・住所」
「財産の内容(不動産の表示は登記事項証明書どおりに記載)」
「誰がどの財産を相続するか」
「日付」
「相続人全員の署名・実印押印」
添付書類の準備相続人全員の印鑑証明書(協議書の日付から3か月以内が望ましい)
財産が多い場合には、財産目録を添付することも多い
財産が多い場合には、財産目録を添付することも多い
協議書の完成・利用完成した協議書を、銀行・証券会社・法務局(登記)などの手続きで使用。
相続人が複数いる場合、原本は1部、相続人ごとにコピー配布するのが一般的。
相続人が複数いる場合、原本は1部、相続人ごとにコピー配布するのが一般的。
注意点相続人全員が参加していない協議は無効。