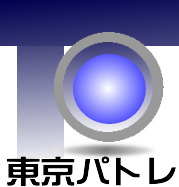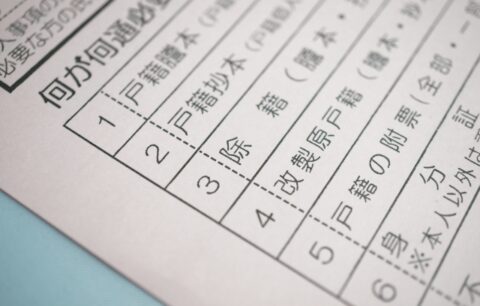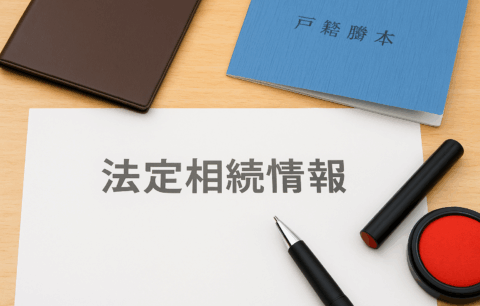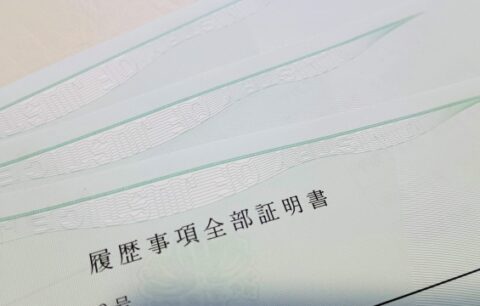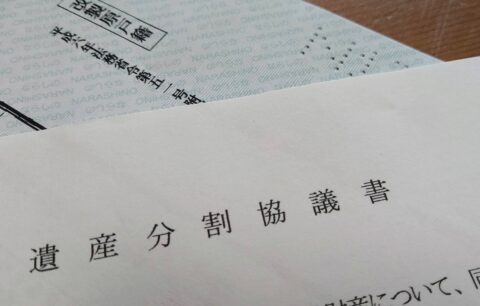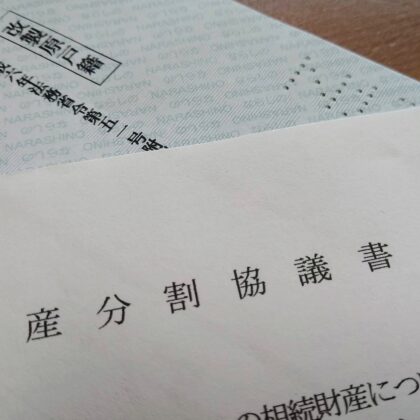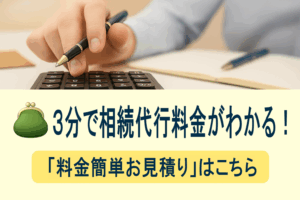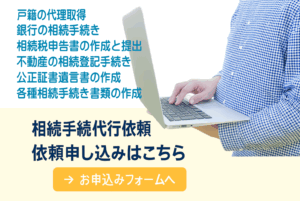相続人の範囲とは?法定相続人を確定する方法
相続手続きの出発点は「誰が相続人か(法定相続人の確定)」です。
ここが曖昧なまま財産の分配や名義変更を進めると、のちに無効・差し戻し・やり直しのリスクが高くなります。
本記事では、民法上の相続人の範囲と、実務での“確定のしかた(戸籍収集~法定相続情報一覧図)”を、初めての方にも分かりやすく解説します。
1. 法定相続人の基本構造(順位)
- 配偶者(法律上の婚姻関係にある者)は常に相続人(内縁の配偶者は含まれません)。
- 第1順位:子(実子/養子/認知された子)。子が亡くなっていれば代襲相続で孫。
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)。第1順位がいないときに相続人。
- 第3順位:兄弟姉妹。第1・第2順位がいないときに相続人。兄弟姉妹が亡くなっていれば代襲相続で甥姪(再代襲はしません)。
ポイントは「配偶者+(第1~第3順位のいずれか)」の組合せで相続人が決まること。子がいれば直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。

2. 相続人に該当する人・しない人の典型例
- 胎児は生まれたものとみなされ、子として相続人に該当(死産の場合は除く)。
- 養子は相続人(普通養子・特別養子ともに)。特別養子は実親との親族関係が切れます。
- 認知された子は相続人。認知の有無は戸籍で確認します。
- 半血の兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ)も相続人になり得ます。
- 内縁関係の配偶者は相続人に含まれません(遺言等での配慮を検討)。
- 相続放棄をした人は相続人でなかったものと扱われます(家庭裁判所の手続きが必要)。
- 相続欠格・廃除に該当する場合は相続権を失います(戸籍・審判で確認)。
3. 法定相続人を「確定」する実務フロー
相続人の確定は、推測や聞き取りでは足りません。
戸籍等の公的資料で客観的に確認し、法定相続情報一覧図(写し)を作成・取得することで、公的に「この人たちが相続人です」と示すことができ、相続手続きを進めることができます。
3-1 戸籍等の収集(出生から死亡までの連続した記録)
- 被相続人の現在戸籍・除籍・改製原戸籍を、出生まで遡って連続取得。
- 結婚・離婚・養子縁組・認知・転籍などの記載を確認して、子や兄弟姉妹の範囲を特定。
- 相続人側の現在戸籍・戸籍附票・住民票の除票等を取得(氏名・本籍・続柄・住所を確認)。
- 海外在住者がいる場合は、在外公館関係書類、署名証明・アポスティーユ等の要否を確認。
戸籍謄本の広域交付制度(2024年3月1日開始)戸籍謄本の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本(全部事項証明書)などの「コンピュータ化された戸籍証明書」を請求できるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求でき、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて取得できるのがメリットです。
ただし、多くの市区町村では事前予約が必要となっており、コンピュータ化されていない戸籍は請求できないほか、一部利用できないケースや、窓口交付に時間がかかることに注意が必要です。
3-2 法定相続情報一覧図の作成・取得
収集した戸籍を基に、被相続人と相続人の関係を模式化した法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証を受けます。
金融機関や不動産、証券、保険等の手続きで戸籍一式の代わりに一覧図の写しを用いることで、窓口提出が簡素化されます。
- 必要書類の整理 → 一覧図の作成 → 申出書提出(各種書類の添付) → 登記官の確認 → 写し交付。
- 5年間は再交付が可能。
4. 確定を難しくする“ややこしい論点”と対処の道筋
- 再婚・前婚の子:前婚の実子・認知の有無を戸籍で確認。所在不明の場合は住民票・附票、調査嘱託等で追跡。
- 代襲相続:子が先に死亡→孫。兄弟姉妹が先に死亡→甥姪(再代襲は不可)。
- 養子の重複:普通養子は実親・養親の双方と親子関係。特別養子は実親側が断ち切られるため戸籍で判定。
- 内縁・事実婚:法定相続人ではないため、遺言・死因贈与・生命保険金等での備えを検討。
- 相続放棄・欠格・廃除:法的効果がいつ発生するか、戸籍・審判書で確認して一覧図へ反映。
5. 相続人確定後の相続手続き
相続人が確定したら、財産の内容を把握して、遺産分割や各種名義変更と同時に必要に応じて税務手続きを進めます。
(当事務所では、相続人確定から各手続きまでを同時進行で進めさせて頂きます。)
- 財産調査(不動産・預貯金・証券・保険・負債)
- 財産目録の作成
- 相続税申告の要否判定(軽減適用の可否確認)
- 遺産分割協議書の作成・署名押印回収の進行管理
- 金融機関・証券などの各種手続き。
- 不動産の相続登記手続き(司法書士へ連携)。
- 相続税申告書の作成・提出
6. 依頼時にご用意いただきたい資料
当事務所へご依頼頂く際に、事前に下記のご確認やご準備していただくと、打合せ時に「より正確なお見積り書の作成」やスムーズなご案内が可能です。
- 被相続人(亡くなられた方)と相続人の基礎情報(氏名・生年月日・住所・本籍・婚姻歴)
- 通帳、証券残高、保険証券などの金融資産情報
- 不動産の固定資産税納税通知書・登記事項証明書・権利証の所在
- 借入金、連帯保証など債務の有無
- 遺言書の有無・保管場所(公正証書/自筆証書・保管制度の利用有無)
特に古い戸籍(改製原戸籍や除籍謄本など)を読むのは、慣れないと難しいと思います。
手書きの文字が読めない場合には、拡大コピーやカメラ機能を利用したり、文脈から推測したり戸籍の種類と年式を理解することにより、どこに何が書かれているかの見当をつけやすくなりますが、解読が難しいケースも時々あるのが現状です。先日、広域交付制度を利用して市役所で入手して頂いた戸籍謄本一式をお預かりしたのですが、よく読み込んでみましたら、出生時の戸籍が不足していました。
市役所の担当窓口の方でさえも、手書きの旧漢字をうまく読みこめなかったのでしょう。