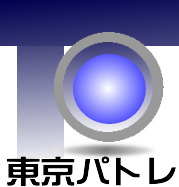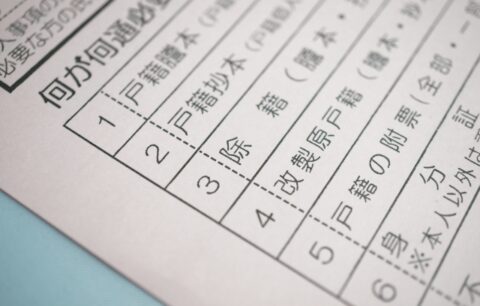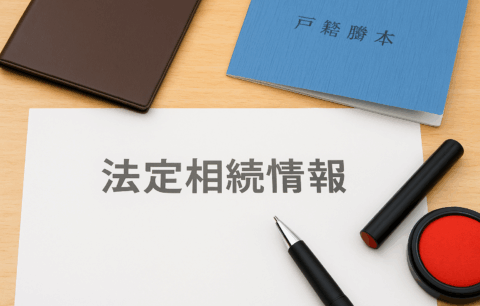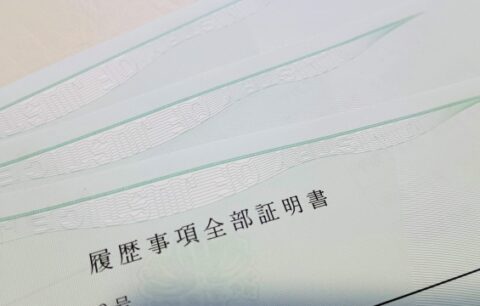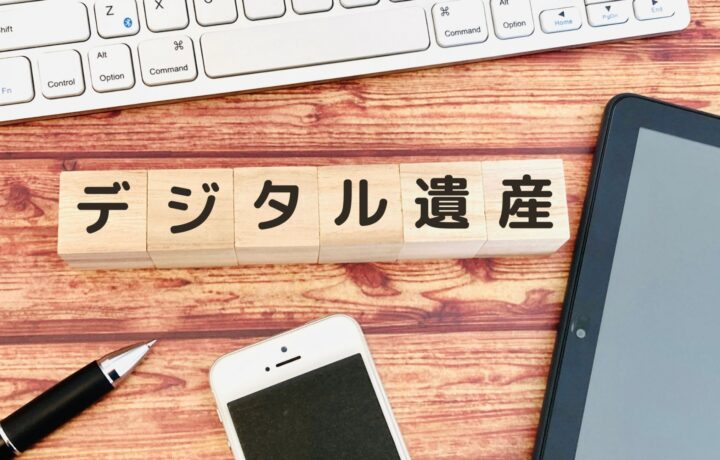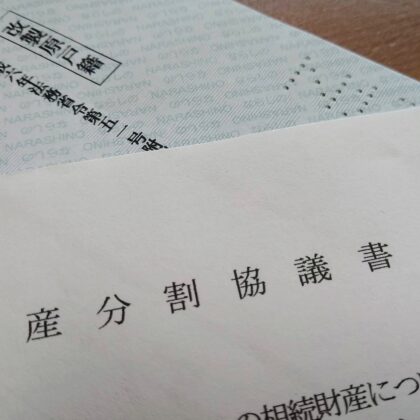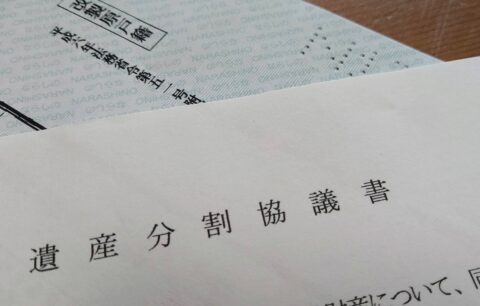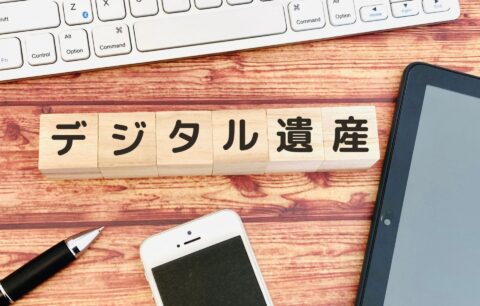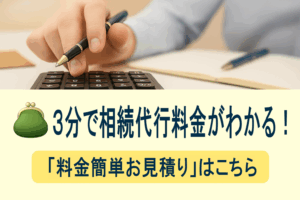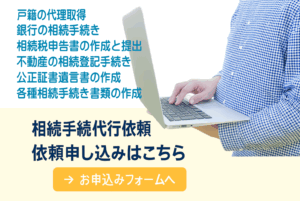デジタル資産(暗号資産・ネット金融資産など)の相続手続きと注意点
ネット銀行・ネット証券・QR決済・ポイント・マイル、そして暗号資産(仮想通貨)やNFTまで・・・「紙による通帳がない資産」は相続する際に特に見落とされやすいものです。
いざ相続が発生したときに「残された家族が気づかない」「相続手続ができない」といったトラブルが起きやすく、相続手続きがすべて終わった1年後に家族が気づいたというケースがよくあります。
本記事では、この記事では、デジタル資産の具体例・相続手続き・注意すべきポイントを解説し、生前にやっておくべき対策などについても照会させて頂きます。
1. 「デジタル資産」とは?
デジタル資産とは「スマホやパソコンの中やインターネット上に残された財産やデータ」のことをいいますが、広い意味ではSNSやクラウドに保存された写真や動画も含まれます。
具体的には、下記のようなものがありますが、近年では銀行、証券会社のほか保険会社も、紙(通帳や保険証書)による書類がないだけでなく、案内などの郵便も届くことが少なくなっているので、アカウント・パスワードの管理がとても大切になっています。
- ネット金融:ネット銀行の預金、ネット証券(株・投信・外貨・債券)、FX/CFD口座、ロボアド
- キャッシュレス:Pay系残高、プリペイド残高、QR/コード決済のウォレット残高、ギフト残高
- ポイント・マイル:スーパーなどのお店ポイント、共通ポイント、航空やホテルのマイル/ポイント
- 暗号資産:ビットコインなどに代表される暗号資産
- NFT:非代替性トークンをいいデジタルアートやゲーム内アイテムなど
- デジタル著作物:動画、ブログ記事、電子書籍などのデジタルコンテンツ
2. 亡くなった人のデジタル資産を把握する方法
デジタル資産は存在に気づけるかが最大の関門です。
そのためには、故人のスマートフォンやパソコンは、デジタル資産の存在を知る大切なヒントです。
処分したり、通信料金を節約しようと回線を解約してしまうと、アクセス不能になりますので、特にご注意下さい。
-
- 個人のスマートフォンやPC:メール、SMS、金融アプリ、クラウドデータ、ブックマーク、家計簿アプリ、取引通知(プッシュ通知履歴)を確認。
- クレジットカードの明細:利用サービスを確認。
- 銀行の入出金履歴:ほかの銀行口座や証券会社の利用状況を確認。
- 電子メールや取引通知:電子マネーなどのキャッシュレスサービスの利用状況・サブスク契約を特定。

3. デジタル資産は相続できるの?
資産の種類によって、相続できるかどうかや手続きが大きく異なるのが、デジタル資産の難しさです。
利用サービスごとに、IDやパスワードなどのログイン方法を家族と共有しておくことが、第一歩です。
- ネット銀行・ネット証券:相続できる(一般の銀行や証券と同様に相続窓口で手続き。ネット専業は郵送対応が中心。)
- キャッシュレス:相続できる場合と相続できない場合がある(ただし、アプリ削除をすると難航するケースあり)
- ポイント・マイル:相続できる場合と相続できない場合がある(規約による。楽天ポイントは相続不可。有効期限を注意!)
- 暗号資産:国内取引所は相続できる(金融庁ルールによる)
4. デジタル資産の相続手続き
デジタル資産の相続手続きは、基本的には通常の相続と同じ流れとなります。
ただし、利用サービスによって手続方法や必要書類が異なるため注意が必要です。
特に暗号資産や電子マネーのようなサービスは、本人のIDとパスワードがわからなければ手続き自体が不可能となるケースもよくありますので、注意か必要です。
- 相続財産の確認
- 相続人の確定:亡くなった方の出生から死去までの戸籍謄本を入手して証明する。
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で合意した遺産分割協議書を作成して、全員の署名押印した書類を作成。
- デジタル資産の相続手続き:利用サービスによって手続方法や必要書類が異なる
5. 「やらなきゃ良かった」よくある後悔する事例
「思いつきでやってしまったため、デジタル資産を相続できなくなってしまった・・・・。」
このような方がやってしまって後悔した事例をいくつか紹介させて頂きます。

結果、3回間違えてログインできなくなった。(規約違反。アカウントロック)
結果、利用サービスアプリとともに認証アプリも消去してしまい、2段階認証ができなくなり復旧不能に。
携帯の電話番号によるSMS認証ができなくなり、ログインできなくなってしまうことに。
8. 生前にやっておくべき対策
デジタル資産は、生前に下記の事項を家族に残しておくことにより、せっかくの財産が消えてしまうことがなくなります。
その場合には、万が一のとき家族に気づいてもらえるように、「スマホのメモ機能」や「パソコンのデスクトップ」に残しておくのも一つの方法です。(ただし、ノートパソコンの場合には、盗難にあったときに取り返しがつかないことになりますのでご注意下さい。)
- 利用サービス名:サービス名やアプリ利用の有無。
- アカウントIDとパスワード:パスワード管理アプリが便利。
- 利用料や利用期間:月額利用料と契約期間とともに、登録している支払方法を記録しておくとGood!
- 相続財産の残高目安:おおよその財産額を記録しておくと、万が一の優先順位になります。
9. 相続手続きを依頼する場合
デジタル資産の相続手続きは、「見つける」「問合せする」「手続きする」この3段階ですすみます。
情報が不足しているケースが多いため、何らかの情報を頼りに利用サービス会社に「問合せする」を確認することから始まります。
- 被相続人と相続人の基礎情報(氏名・生年月日・住所・本籍・婚姻歴)
- 利用していたと思われるサービス名一覧(ネット銀行・証券・ウォレット等)
- クレジットカードの利用明細
- 端末(スマホ・PC・ハードウェアウォレット)
- 利用会社からのハガキや封筒
- クレジットカード類
- メール・SMS・アプリ通知のスクリーンショット
- 家計簿アプリの有無
- 資産管理アプリの有無
- その他の紙のメモなど
結果として、約400万円の投資信託や株式を発見し、奥様が無事に相続することができましたが、これも「火葬する前にスマホの顔認証の解除ができたこと」が発見につながった大きな要素でした。
これをキッカケに、自分自身も妻にスマホ解除の暗証番号は伝えるようにしました。