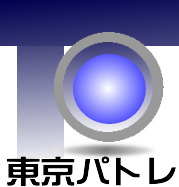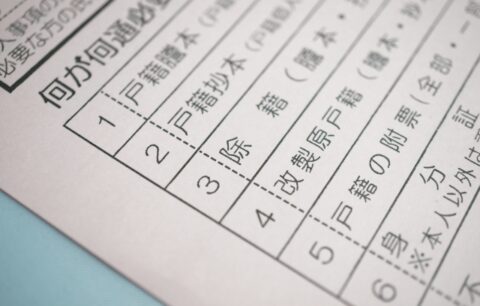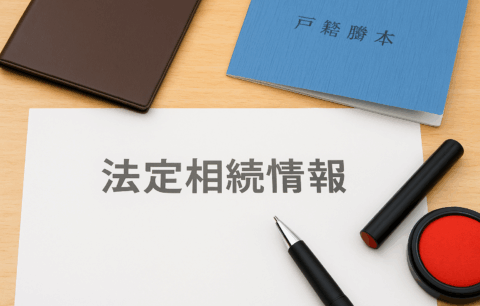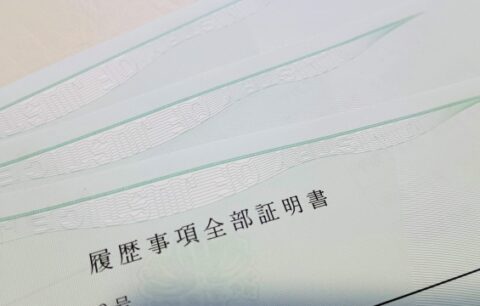土地や建物を相続する人が相続税を納付するときは、相続した時点で『この不動産はいくらなのか』を納税者自身が計算しなければならないことになっています。
具体的には、国税庁が定める評価基準に基づいて計算しなければならないことになっており、大まかには不動産の種類ごとに計算します。
それぞれの不動産の評価額を計算した後に、その不動産が一定の要件を満たすと「評価減(減額)」が認められる場合には、特例による減額を差し引いて最終的な「課税価格計算上の価額」を相続税の申告書の財産評価明細書に記載します。
「不動産の種類ごとの評価方法」 -「 補正・特例による減額」 = 「課税価格計算上の価額」
不動産の種類ごとの評価方法
宅地(路線価方式)市街地にある宅地の多くは「路線価」に基づいて計算します。
評価額 = 路線価 × 面積 × 各種補正率
(補正率には、奥行補正・間口狭小補正・不整形地補正などがあります。)
評価額 = 路線価 × 面積 × 各種補正率
(補正率には、奥行補正・間口狭小補正・不整形地補正などがあります。)
宅地(倍率方式)路線価が付されていない地域では固定資産税評価額に一定倍率を掛けます。
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
家屋(建物)原則として「固定資産税評価額」
貸宅地・貸家建付地借地権や借家権が設定されている場合、評価額から一定割合を控除します。
< 例 > 貸家建付地の評価額 = 宅地評価額 × (1 – 借家権割合 × 賃貸割合)
< 例 > 貸家建付地の評価額 = 宅地評価額 × (1 – 借家権割合 × 賃貸割合)
農地農地は地目や地域に応じて評価。
市街地農地 → 宅地並評価
純農地・中間農地 → 近傍農地の売買価格などを基準に算定。
市街地農地 → 宅地並評価
純農地・中間農地 → 近傍農地の売買価格などを基準に算定。
不動産の評価減となる例
小規模宅地等の特例(居住用)被相続人が住んでいた宅地を相続人が引き続き居住する場合、最大80%評価減
小規模宅地等の特例(事業用・貸付事業用)事業や賃貸事業に使っていた土地についても、最大50〜80%評価減
貸家建付地宅地に貸家が建っている場合、借家権割合を考慮して20〜30%程度減額
貸宅地(借地権設定済の土地)他人に貸している土地は、借地権相当分が控除され評価減
不整形地補正三角形や細長い形など、利用効率の悪い土地は補正率により評価減
奥行長大補正・間口狭小補正奥行が深すぎる土地や間口が狭すぎる土地は減額補正
セットバックを要する宅地道路後退部分は宅地として利用できないため、その部分を控除して評価
高低差のある宅地道路より高い/低い位置にあり利用が不便な場合、評価減の補正
市街化調整区域の宅地建築制限があるため、利用価値が低く評価額も下がる
文化財指定や建築制限のある土地歴史的建造物がある、用途制限が厳しいなどの場合は減額
無道路地(接道義務を満たさない土地)道路に接していない土地は建築不可のため、市場価値が下がり評価減
私道部分の宅地公道に提供されている私道部分は、利用制限があるため減額評価
建築基準法上の制限地(防火地域・高度地区など)建築規制が強く、利用制限がある場合は補正により減額
がけ地・傾斜地利用しにくく宅地造成が必要な場合は、がけ地補正率を適用して評価減。
市街地山林・原野宅地転用が難しい地域は利用価値が低く、宅地並みの評価とならず減額
大規模地補正一般的に需要が少ない広大な土地(例:500㎡超)については、1㎡あたりの単価を下げて評価
市街化調整区域の農地・山林宅地転用が制限されるため、宅地並評価ではなく農地評価・山林評価が適用され、結果的に評価減
借地権付き建物借地上の建物は所有権が制約されるため、土地・建物ともに評価が低くなる
地役権設定地他人の通行権や採光権などが設定されている場合、利用制限があるため減額される